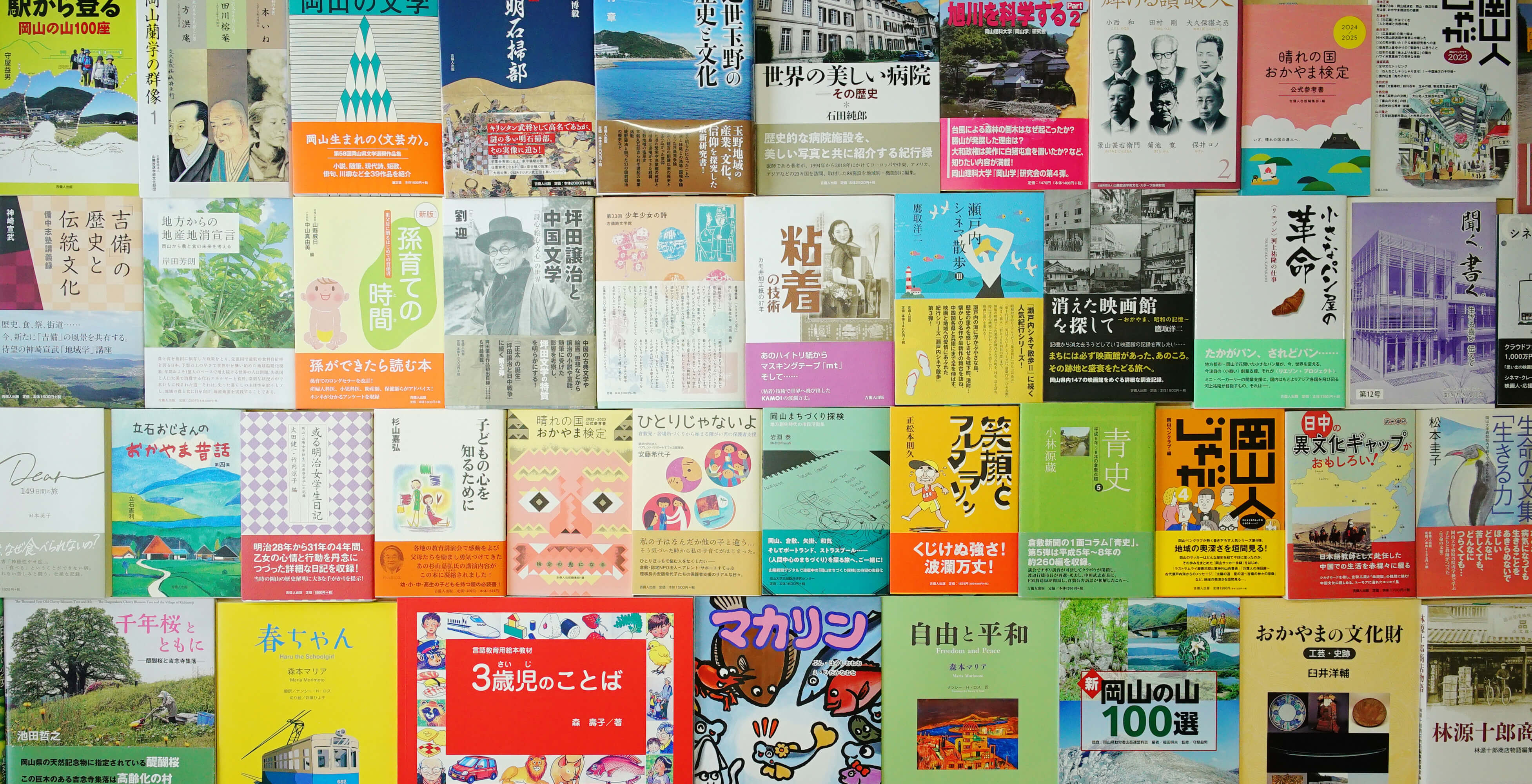第2回本は生きもの。だから心を込めて。
(株)三門印刷所会長・三村義人さん
(株)三門印刷所会長・
吉備人出版の創業以来、刊行物を印刷していただいている(株)三門印刷所。
60年以上も印刷業に携わり、現在も会長として現場で書籍印刷の指揮を執られている三村義人さん(82歳)に話を聞きました。

30年前に創業して初めて本を印刷してもらったのが三門印刷所でした。
その頃は文字編集の専用機を導入していました。
それと、印画紙の文字を打ち込んで切り貼りをして組版を作成する「写植」もあり、鉛の活字もまだあったころです。
三門印刷所は会社設立から100年を超えているそうですね。
私の祖父・三村竹次郎が大正3年(1914)に岡山市の石関町で三村活文堂印刷所を始めていますから、昨年110年を迎えました。
印刷所としては、岡山市内では一番古いのではと思っています。
石関町にあった建物は、昭和20年(1945)の岡山空襲で焼失したので、二男だった私の父が昭和29年(1954)に独立して岡山市北区の上伊福で三門印刷所を立ち上げました。
現在の会社がある中区高屋には、昭和51年(1976)に移転しました。
三村会長が三門印刷所で仕事を始めたのは?
昭和35年(1960)に、私が高校を卒業してから父の印刷所を継ぎました。
そのころ工場には大きさの違うたくさんの鉛の活字があり、木の棚に収められていました。
その活字で版組をしていた活版印刷の時代でした。
それから写植、編集専用機(モトヤ)、パソコンの編集ソフト(DTP)になり、製版は銅販からフィルムへと変わってきました。
これまでの65年の間に印刷技術はめまぐるしく進化し、印刷機も時代に対応して新しくしてきました。
書籍の仕事はいつ頃からですか。
若い頃は、学校の会報やPTA新聞、同人誌、歌集など、印刷業界でいう〝文字もの〟を多く印刷していました。
ページ数の多い本格的な書籍の仕事を始めたのは、昭和56年(1981)ごろに手帖舎の岸本徹社長と知り合ってからです。
手帖舎は詩集や句集、随筆などを刊行する出版社でした。
手帖舎の編集を担当していたのが、宮園洋さんでした。
宮園さんは東京消防庁の機関誌、詩集や評論集の編集を専門に手がけていたほか、詩集を専門にしている思潮社の装丁をするなど、東京の印刷物の仕事をされており、編集やデザインにかけてはプロでした。
私はこの二人、岸本徹さんと宮園洋さんに書籍の印刷やデザインのことを教えてもらいました。
吉備人出版の初期の装丁デザインは、ほとんどを宮園さんにお願いしていました。
宮園さんのデザインの指示書は、特徴ある手書きの文字で、詳細に書かれていたのを覚えています。
写植時代のころのものは、そうでしたね。
岸本社長や宮園さんから原稿と一緒に受け取った指示書の内容は、最初のころには書いてある指示の意味さえも分からず、何度も聞いて確認しながらつくっていました。
経験を積むにつれて、自分でも少しずつ工夫して本づくりをするようになっていきました。

「〝文字もの〟の三門印刷所」になっていったということですね。
ページ数の多い本や文芸誌などを受注するために、早くから文字組や編集のできるモトヤの組版機を導入し、〝文字もの〟に対応できるようにしました。
チラシなどの印刷とは違って本は残るものです。
しかも奥付にわが社の社名が刻印されることもあって誇りにも思い、〝書籍印刷が得意な印刷所〟にしていこうと考えたんです。
長年の書籍づくりに、どんな思いを持っていますか。
振り返って考えてみると、とにかく「本は生きもの」だと思います。
本はつくり方によって生きもするし、死にもします。例えば、紙には「縦目」「横目」があって、これを間違えると、ページをめくりにくい〝さばき〟の悪い本になります。
紙ごとに「目」を読んで、紙の断裁の方向を決めていかなければなりません。
こうした紙の目のことは基本的なことですが、本の大きさ(判型)、ページ数、内容によっても本文の紙の厚さを決め、カバーや表紙、見返しの紙の種類や厚さを選び、必要な紙の枚数を仕入れていかなければなりません。
本は紙の厚さや種類の組合せが悪ければ、ごわごわしたりペラペラしたりして、使い心地の悪い本になります。

本を持ったときに〝手になじむ本がよい〟ということですね。
デザイナーさんの指示書で進めることもありますが、その指定について、この本はページ数が多いから本文はもう一段階薄い紙にした方がよいのではなどと、アドバイスすることもあります。
長年の経験からくる〝職人〟としての助言ですね。
私が経験してきたことを生かせて、少しでもよい本になれば、それでよいと思っています。

今後、書籍はどんなふうになっていくと感じていますか。
紙とデジタルの本は、平行して進んでいくでしょう。
でも、私にとって本は、紙のものですね。紙の本には温もりがあり、人の温かみや思いがあると思います。
書いた人、つくった人の思いが込められていると思います。
だから私は、チラシは床に置けても、本は机の上、棚の上に置くもので、床には置けません。そういう〝もの〟ですから、これからも本は心を込めてつくりたいと思っています。
引き続き、よろしくお願いします。
- 三村義人(みむら よしと)
-
昭和16年(1941)生まれ。岡山県立岡山東商業高等学校卒業後、父が経営していた三門印刷所に就職。
WEBサイト:株式会社三門印刷所
昭和44年(1969)に(株)三門印刷所に社名変更。専務、社長を経て、平成31年(2019)から会長。