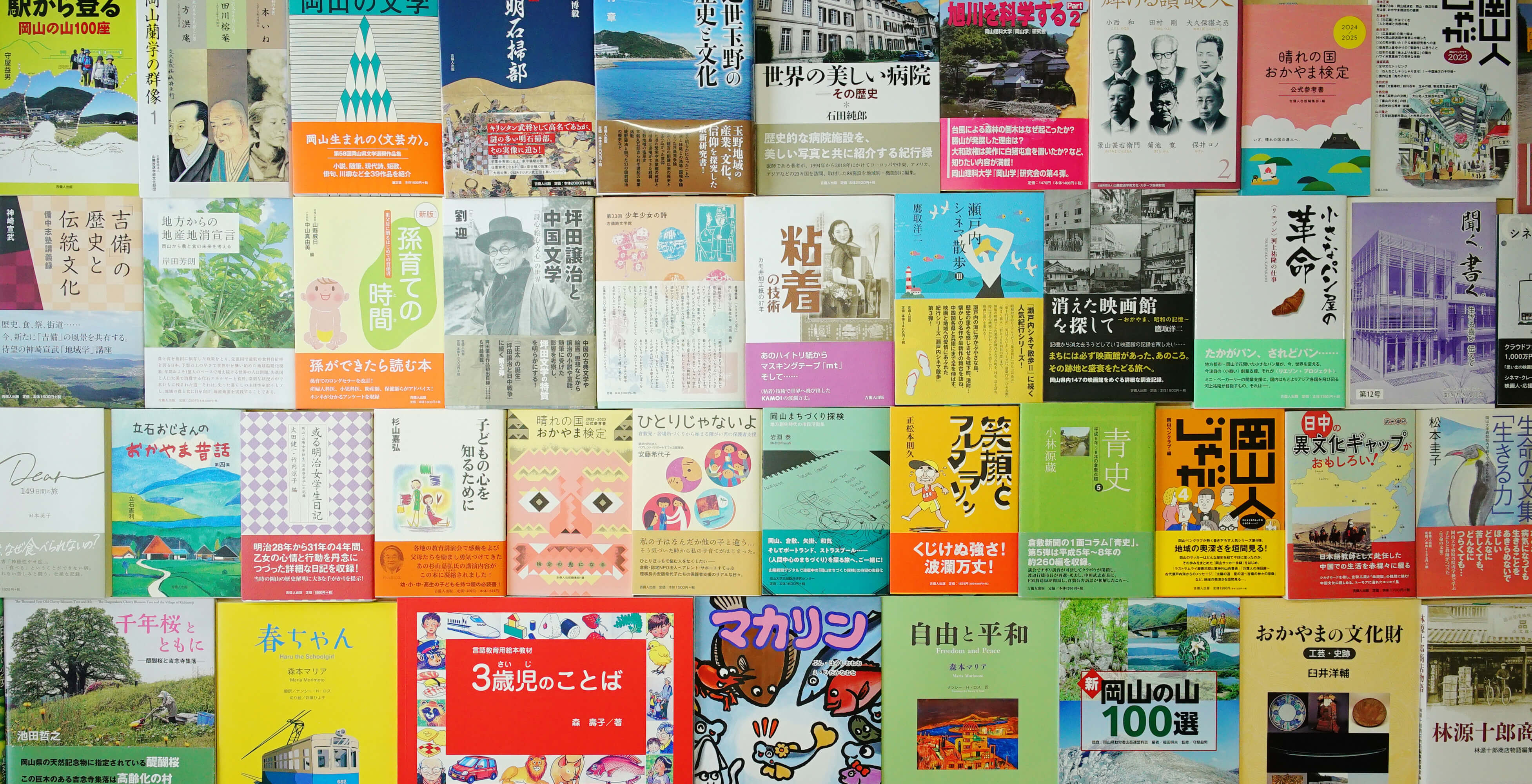プロローグ吉備人のその前(1993年~1995年)

社名は吉備人
吉備人出版は2024年で設立30年目に入った。「吉備人(きびと)」という会社組織にしてからは30年目だが、その前から活動そのものは始まっていた。
1992年の暮れ、岡山リビング新聞社を退職していた金澤健吾と水原晶代が、岡山大学津島キャンパス近くの松原電業第2ビルという名のテナントビルの2階に部屋を借り、編集プロダクションを開業した。
北側の部屋は日が当たらず、事務所開きの師走のその日は肌寒かった。応援してくれる人を数人呼んでのささやかな門出だった。独立して果たしてやっていけるのだろうか、という不安も大きかったが、それ以上にわくわくする期待感のほうが強かった。
のちに代表となる山川隆之も合流することは決めていたが、その年の1月から「リビングくらしき」を発行する倉敷リビング新聞社勤務(当時は、岡山リビング新聞社と倉敷リビング新聞社は別会社で、出向という形での勤務だった)になったこともあり、このタイミングで会社を辞めることもできず、倉敷市役所近くにあったリビングくらしきの事務所から仕事帰りに津島の事務所に立ち寄り、二人の状況を聞いたりする時期が続いていた。当時は取材の請け負いが中心の業務で、瀬戸内海経済レポートやKG情報出版、山陽新聞社出版局などからの仕事を受けていた。社名は「L.I.C(リック)」としていた。LOCAL、INFOMATION&CULTUREの頭文字を取ったのだ。

95年3月31日付けで岡山リビング新聞社を退社した山川は、翌日の4月1日から吉備人に移った。合流し、本格的なスタートをということで、社名を「L.I.C」から「株式会社吉備人」として法務局へ届けた。
「吉備人=きびと」は吉備の国とそこで生きる人たちを示す造語だ。社名については、山川と金澤がふたりでいろいろ考えたのだが、この名前が一番気に入った。
当時、山川は雑誌「東京人」が好きで、こんな雑誌を岡山でつくれないか、などと考えていた。東京人に対して「岡山人」ではなんとなく野暮ったい。岡山は、古く吉備の国といわれていて、「吉備」を使った社名はたくさんあったが、人をくっつけた社名はなかった。「吉備人」漢字で書いたとき、これだと思った。
問題は、これをどう読ませるのか。
「きびじん」「きびびと」……。「人」を「と」と読ませることから発想した。小学校時代に公人という名の友人がいて、「公人」と書いて「きみと」だった。「人」は「と」。それで「吉備人」を「きびと」と読ませることにしたわけだ。
早速自作のデザインで名刺をつくった。吉備人の文字は見出し明朝体をつかった。
名刺を渡した相手は、どう読むのかわからない。「吉備の国の吉備に人と書いて、きびとです」
そうすると、「へえ、いい名前ですね」とほめてくれる。一度説明すると、たいていの人は覚えてくれる。
ある人は、「吉備人」はお米や酒のネーミングにぴったりだから、商標登録しておいたら、なんてアドバイスしてくれる人もいた。「いけるかもしれない」と、ちょっと心動いたが、商標登録はしていない。
編集プロダクションで基盤づくり
国道53号に面した事務所ビルには、1階にはコンビニや洋食屋、2階に音楽教室や美容室、歯科医院が入っていた。
机やテーブル、キャビネット、ロッカーなどとりあえず必要なものは、水原の仕事先の岡山学芸館高校で使わなくなったものを譲り受けた。色やサイズなど妙にちぐはぐで統一感はなかったが、とりあえず仕事はできるような状態にはなった。
その後も、知り合いの事務所や教室などで使っていた事務用の机、ロッカー、キャビネットなど、いただけるものはどこまでも取りに行った。その中には、広島の化粧品会社のオフィスや津山のカルチャー教室などもあった。
払い下げなので古くて重いスチール製のものが多く、津山のカルチャー教室でもらった机を運んでいるときに山川がギックリ腰になり、やっとの思いで岡山に戻り、事務所近くの整骨院に駆け込んだ。
とはいえ、人数分の机や資料入れなどは一応そろい、なんとなく事務所らしくなった。
雑誌や本など制作物は自前で組版できるようにしようと、当時出始めて間もなかったMacのDTPシステムを一通りそろえることにした。
PowerMac7200にクオークエクスプレス3.3にイラストレーターVer.5.5、フォトショップVer.5.0、エプソンのPSプリンター、スキャナー。これで印刷の手前までは全部自前でできるシステム構成だった。トータルで200万円を超すシステムを、リビング新聞社にコピー機やファクシミリを納入していた関係でよく知っていたキヤノンシステム&サポートとリース契約した。
システムは整ったのだが、実戦で使いこなすには経験も知識も乏しかった。なんとかマスターしなければと、マニュアルをそばにMacにずっと向かい合っているうちに、山川はMacの前に座ると吐き気を催すようになっていた。
キャノンのサービス担当の女性は、それでも根気強く指導、サポートしてくれ、編集、制作を請け負った住宅雑誌の特集部分のレイアウトからクオークでつくっていくようになった。

出資者を募る
編集工房吉備人という名前で、とりあえず船を漕ぎ始めた。会社経営などまったく素人の3人組。何からどう手を付けていっていいのかわからないことだらけ。書店へ行き、会社経営の入門書を買い込んでにわか勉強も始めた。
勤めていた会社の上司に、何からやればいいか尋ねてみたところ、経営計画を立てろとアドバイスされ、入門書片手に経営計画なるものを作ってみた。
そのころは、地元情報系出版社の住宅情報雑誌の特集ページを請け負ったり、経済誌の別冊の仕事を受けていたり、定期的な仕事もいくらかは入っていたが、経営計画に盛り込んでいくには、まだまだ足りない状態だった。
3人とも家族を養い、ここで稼いで生活をしなければならない。事務所の家賃や諸々の事務所経費を払い、残りを人件費に割り当てるのだが、とてもではないが生活できる金額ではなかった。
1月や2月は、前の会社の退職金などでなんとかなったが、会社を運営していくための運転資金などは皆無だった。名目は株式会社だったものの、資本金は現金では少なく、持っていた車やパソコンなど原物支給で換算したものが多かったため、会社はスタートしたがあっという間に資金ショートしてしまった。
やむにやまれず、元上司のNさんに状況を相談した。Nさんは岡山リビング新聞社をやめた後、広島に本社がある化粧品会社の重役に招かれていた。
「出資してくれる株主を探して、とりあえずのお金を作ったら」
こうアドバイスしてくれ、自らも100万円を出資してくれ、何人か協力してくれそうな人も紹介してくれた。
知り合い、先輩、兄弟…声をかけることができそうな人に無理を言った。ありがたいことに、資本金1000万円のうちの約50%をそういった知り合いからの出資によって調達することができた。
これで当座の現金は手にすることができた。
(文・山川隆之)